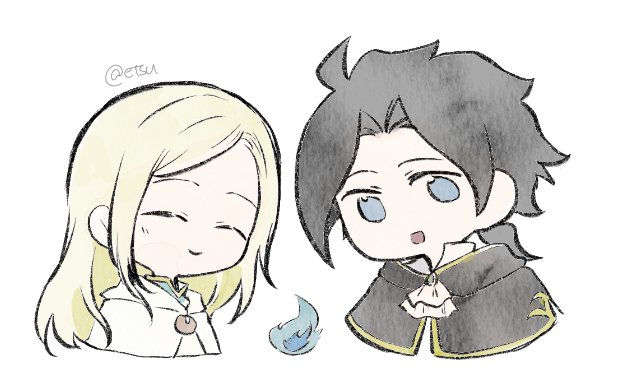
2024/10/15
オフィとサイ
privatterで公開していたお話
サイラス1章部分はどこかで公開
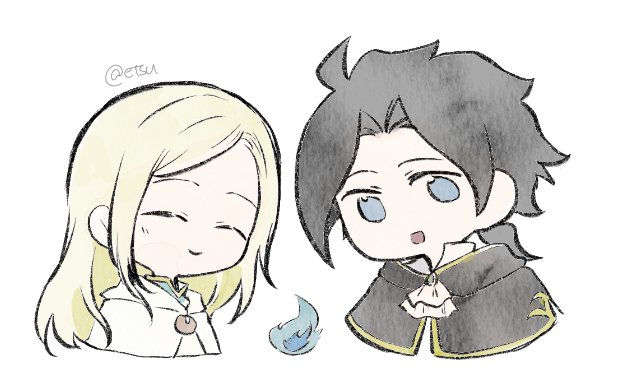
オフィとサイ
privatterで公開していたお話
サイラス1章部分はどこかで公開
衣擦れの音に寝台の軋む音が重なった。
息をつく。目蓋を閉ざせば、つい数時間前に見ていた聖火の試練の光景が眼裏に蘇る。
サイラスの傷を治療してくれた神官は、名をオフィーリアといった。
リバーランドの戦災孤児で、ここフレイムグレースの大司教に引き取られ、神官になった彼女は、ある事情の下、夜間ながら町を出歩いていたという。
数日もしないうちに、神官リアナが式年奉火のため、聖火の試練を受ける。しかし、彼女の父・ヨーセフ大司教はここ数ヶ月体調を崩しがちで、この数日は喀血も見られ、容態が悪い。
このオルステラにおいて、肉親とのつながりは貴重だ。唯一の肉親となればなおさら、心配は募る。
加えて、式年奉火は聖火教会史上においても重要な位置を占め、成人したばかりの神官がたった一人で完遂するには障害も多い。
重責と、儀式の間に家族を失うのではないかという不安、恐れ。そういった精神的負荷がリアナの顔を曇らせていると思い──オフィーリアとリアナは義姉妹であり、家族である──そこで、オフィーリアはリアナが父親と共にいられるよう、儀式の代行を考えたという。
聖火の試練を受け、聖火を持ち帰る。すなわち、自分こそが儀式を担える神官だと示せば、問題はあるまいと──彼女はそう考えたのだ。
式年奉火は、二十年に一度行われる、聖火教会の重要な儀式だ。
セントブリッジ、ゴールドショア、そしてここフレイムグレースに聖火は実在する。蒼とも碧にも輝く炎は、油や薪などの燃料を必要としない代わりに、注ぎ火──文字通り聖火を注ぐことで炎を維持する。
この聖火なるものは、事実、邪気を払うとされ、魔物を街に寄せ付けない。加護を受けられるから人々は炎を信じ、炎もまた、火を注がれる限り燃え続ける。
サイラスはアトラスダムで生まれ育ったので、この『火を注ぐ』という行為にも、聖火自体にも、特別な感情は持ち合わせない。
ただ、彼には純粋なる興味があった。
家族から、街の住人から、あるいは講義で語り聞くたびに不思議だった。聖火教会にまつわる書物は、学者とならなければ読むことを許されていないものも多く、そのくせ、遠い、他国でもある故郷においても『聖火の加護』という言葉は日常的に耳にする。
幼き日の自分の問いかけに、旅人や両親、教師は多くの回答をくれたが、やはり自分の目で確かめる以外に納得はできなかった。
学者の操る火炎とは何が違うのか。なぜ二十年に一度なのか。炎の何を以てして、注がれたとするのか。
そこにあるものに疑念を抱くというと聞こえは悪いが、全ては好奇心から転ずる疑問だ。
とどのつまり、オフィーリアは、サイラスがかねてより抱いていた興味に触れる人物に違いなかった。
初対面の女性についていくことなど、普段ならばしないサイラスだが、今回ばかりは治療の礼もあったし、事情を伺うや、軽い足取りで彼女についていき、成り行きで試練にも参加した。
一度開いた本を、読み終えるまで手放せないのと同じだと告げると、オフィーリアは瞬きを数度繰り返した後、雪が解けるように淡く微笑み返した。
しかし、試練自体はなかなか過酷なものだった。
長丁場の戦闘となったため、オフィーリアを大聖堂まで送り届けた後、なんとか宿へ戻り──書ける限りのことを書きつけて、横になっている。
脚の痛みが酷い。サイラスは何度か寝返りをうってこれを誤魔化していたが、やがて、試練で見たものを思い返す方向に意識を移した。
なにせ、試練で立ちはだかったのは、古代兵器だったのだ。
(聖火の声……と呼ぶべきか。あれはまるで人が話しているかのようだった。信仰がそれを可能に? まさか! ではなぜ私まで聞こえたのか……)
カタカタと窓が鳴った。風が強くなったのだ。
深夜には吹雪くだろうと、行き違えた狩人の呟きを思い出す。サイラスはシーツを肩まで引き上げ、仰向けから横向きに体勢を変えた。宿全体が暖炉で暖められているとはいえ、窓側に近いので、寝台にいるとやや寒い。
部屋の隅に申し訳程度に用意された机の上に、先程まで灯していた手燭と、蓋の閉じられたインク瓶、ペン先を整えられた羽根ペンがある。
起きて、続きを書き留めようか。サイラスは迷う。
(無詠唱で古代兵器を召喚したということは、聖火と古代兵器になにか関係が? 聖火とはただの蒼色の炎と思っていたが、例えば仮にあれが聖火神なる声だったとして……古代兵器との戦闘を試練とするのは、なんとも、容赦のない試験だな)
古代兵器とは、破壊しても時間経過で再び動き出す、半永久的に可動する人形のことを指す。主にオルステラ大陸の遺跡や洞窟で観測され、遺跡調査に出かける学者はもれなく彼らと対峙する。そこで命を落とさなかったものが後世に書き残したからこそ、サイラスもその存在を知っていたわけだが──フレイムグレースにもその姿があるとは思わなかった。
(入口を見張る騎士達も、あれは侵入者を防ぐというより、外側に出ていかぬための見張りなのかもしれないな……)
聖火教会の内部事情は、ごく一部の者しか知り得ない。だからこれはあくまで推測の域を出ず、サイラスも単身で調査に乗り出るつもりはなく、この話はひとまずここでおしまいとした。
戦闘後の興奮で、血の巡りも早いのだろう。
身体が温まれば、眠気が忍び寄る。
このまま寝てしまうか──サイラスがようやっと目蓋を落としたその時、部屋の外から声が掛けられた。
「学者先生、神官様がお呼びですよ」
この町で自分を訪ねてくる相手など、一人しか思い浮かばない。
宿の主人にはすぐに向かうと返事をして、眠気を振り払うように身を起こした。
「お休みのところ、すみません。サイラスさん」
「構わないよ、オフィーリアくん。それで、私に用事とは?」
暖炉の前で温まっていた彼女は、サイラスが階上から降りてくる音に気付き、腰を上げた。採火灯と聖火教会の杖を持ち、白いローブと昼間と何一つ変わりはない。大きな荷物もあるようには見えなかったので、どこかへ出かける話をしにきたわけではないだろう。
せっかくなのでそのままロビーを使わせてもらうことにして、オフィーリアともども着席する。
実を言うと、彼女が何を伝えに来たのか、サイラスは既に分かっていた。
「式年奉火の旅に出ることになりました」
静かにオフィーリアは結論を述べた。
「おめでとう。キミの勇気と優しさが、道を開いたと言うわけだ」
「ありがとうございます。それで……式年奉火を支援してくださる商会の方とはお話がつきまして、次の目的地セントブリッジにて落ち合うこととなりました」
式年奉火は聖火教会の中でも重要な儀式となる。魔物も賊も多いオルステラでは、単独踏破をするには障害が多く、そのため、懇意とする商会に物資や警護の補助を頼むことが多い。
今回、その大役を担うはずだった義姉妹に代わり、彼女が実施することとなった。商会としては事前の打ち合わせと大きく変わり、別途、調整が必要となったのだろう。……旅の物資となるとそこまで違いはないように思うが。
「では、キミはしばらく件の聖火騎士と旅を?」
「ええ。それと、」
にこりとオフィーリアは微笑む。
「サイラスさんの同行にも問題はないと言われました。商会の方で傭兵を雇うより、その方が都合が良いだろうと」
「それはいい!」
サイラスの弾んだ声と、焚き火の爆ぜる音が重なる。
──予測した通り、オフィーリアはサイラスの式年奉火同行の許可が得られたと伝えに来たのだ。
「ありがとう、オフィーリアくん。初めて辿り着いた町で、このような幸運に恵まれるとは思わなかった」
「今回のことは、サイラスさんのおかげもありますから。ですが、よろしいのでしょうか? サイラスさんも目的があって旅をなさっているはずでは……」
「そうだね。私も旅の目的はある……が、先を急ぐことではない。是非とも同行させてもらいたいね」
彼女が携えた採火燈へ視線を落とし、サイラスは何度も噛みしめるようにうなずいた。
「勿論、道中、私の目的地の近くを通るようなら、共に来てもらえると助かるがね」
「ええ、勿論」
ああよかった、とオフィーリアは安堵の息をついた。
彼女が夜分ながらサイラスの元を訪れたのは、サイラスの申し出に対しての返事と、旅の出立日の相談をするためだったようだ。
旅立ちの予定について簡単に話を詰め、吹雪の和らいだタイミングで彼女は、この辺りで、と席を立つ。
「オフィーリアくん。最後に一つ、いいかな」
「なんでしょう?」
呼び止めると、素直に彼女は座り直した。
「キミの戦いぶりは試練で見た通り、私にとっても頼もしいものだった。……それだけに、これだけは伝えなくてはと思ったことがある」
オフィーリアはサイラスの話を静かに聞いた。その手は聖火教会のモチーフの入った杖を持ち、こころなしか、先程よりも強く握りしめられているような気がする。
「この先の旅路では、魔物や、はたまた賊との戦いとなる。その時キミはどう動くか、明日の朝聞かせてほしい。聖火騎士を同行させ、彼に戦闘を任せるのか、キミ自身も戦うのか」
試練での振る舞いを見る限り、彼女にも戦闘の心得がある。これは心配というより相談だ。
「私はこの通り、近接戦闘には不向きなのでね。その上、詠唱中は何もできない。キミ自身が戦わなくてはならない場面も出てくるから……」
「……そうですね」
オフィーリアはやや顔を俯かせたが、すぐに顔を上げた。
「では、サイラスさんが詠唱中は私が前に出ます」
「ん?」
「魔物の対処についてはこれまでのように、サイラスさんから教えてもらいますから、大丈夫です。負けません!」
「う、うん。……ではそのように」
家族との話し合いも落ち着き、思いやりと勇気だけで飛び出した彼女も冷静さを取り戻した頃合いだと判じたわけだが。
こちらの戸惑いを悟り、オフィーリアは握りしめた拳をさっと膝の上へ戻す。
「……大丈夫です。フレイムグレースにも賊の方々が押し寄せることもあります。聖火騎士や狩人の方が対応する姿も何度か見ています」
「そうか。しかし今度は、キミが対処しなくてはならない。迷えば命取りとなる場面も出てくるだろう。……それでも、戦えるかい?」
「はい」
オフィーリアの佇まいは、しんと雪が降り積もった後の静寂を想起させた。何者にも踏み荒らされていない、新雪が降り積もった真っ白の雪原。
「リアナの分まで、頑張ります」
慈愛に満ちたその微笑みは、この先多くの者に向けられることだろう。
「では……改めて、これからよろしく頼むよ。オフィーリアくん」
「こちらこそ。よろしくお願いしますね、サイラスさん」
そうして今度こそ二人は立ち上がり、宿の戸口で別れた。